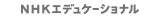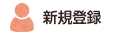夜中、子どもたちが違う時間に起きるので、寝不足に…
子ども2人を育てていますが、夜中、子どもたちが違う時間に起きるので大変です。
上の子は、夜起きると「ママ」と連呼して、パパではだめです。寝るときに外に行きたがって、ママがだっこして出かけることもあります。下の子は、ミルクを飲んでもすぐにゲップが出ないので、ミルクで起きて、1時間半後にゲップを出したくて泣いて起きます。
ある日は、上の子が3回、下の子が4回、違う時間に起きました。この状態だと、親は日中昼寝をしないと倒れてしまいます。今は育休中なので、1時間ずつ時間を決めて午前・午後、交代で昼寝しています。いつまで続くのか、改善の方法がないかと思っています。
(お子さん1歳9か月・3か月のパパ)
上の子は、夜起きると「ママ」と連呼して、パパではだめです。寝るときに外に行きたがって、ママがだっこして出かけることもあります。下の子は、ミルクを飲んでもすぐにゲップが出ないので、ミルクで起きて、1時間半後にゲップを出したくて泣いて起きます。
ある日は、上の子が3回、下の子が4回、違う時間に起きました。この状態だと、親は日中昼寝をしないと倒れてしまいます。今は育休中なので、1時間ずつ時間を決めて午前・午後、交代で昼寝しています。いつまで続くのか、改善の方法がないかと思っています。
(お子さん1歳9か月・3か月のパパ)
りんたろー。さん(MC) 1人でも大変なのに、2人で起きる時間がずれるとほんとうに大変ですね。
丸山桂里奈さん(MC) 「外に行きたい」ってなると、1回外に出かけて、また帰ってきて大変だと思います。
―― 上の子がなかなか眠れないのは、なにか考えられますか?
睡眠の環境を整える
回答:柳沢正史さん 基本となる睡眠の環境を考えてみてください。大人も子どもも、シンプルに「暗くて静かで朝まで適温」が大事です。 睡眠の環境① 真っ暗にする 眠れないのは光が原因かもしれません。光環境は大事なのです。光に敏感な子もいるので、部屋を真っ暗にします。例えば、部屋で赤ちゃんや子どもが見えるぐらいだと明るすぎる可能性があります。場合によっては、電気機器のパイロットランプにテープを貼って消す、カーテンは遮光カーテンで必要ならクリップなどでとめる。それぐらい真っ暗にすることを試してみてください。 また、起きて授乳やオムツ替えなどをする場合は、必要最低限の暗い照明で行います。 睡眠の環境② 少し雑音があったほうが寝やすい 音環境も大事です。ホワイトノイズといわれる雑音は、眠る上でよい効果があります。 「シー」「ザー」といった、50~60デシベルのノイズは、専門用語で「マスキング」といわれ、少しノイズがあると逆にほかの音が聞こえにくくなります。その特性を利用して、あらかじめノイズを出しておくと、無音よりいい場合があります。例えば、エアコンの静かな風の音でもいいでしょう。小川のせせらぎなどの自然音に近いノイズを出す機器もあります。 睡眠の環境③ 眠るルーティンを作る もうひとつ大事になるのは入眠儀式です。英語で「ベッドタイムルーティン」といいます。いってみれば、「眠る準備」を体で覚えるわけです。幼い子どもでも、覚える能力があります。 例えば、もう少し大きな子どもであれば、歯を磨いて、パジャマに着替えて、親が絵本の読み聞かせをして、眠りにつく。毎晩同じように繰り返すと、「自分は眠る時間」だとわかっていきます。
―― だっこして寝かしつけるのはどうでしょうか?
だっこがルーティンになってしまうことも
回答:柳沢正史さん 私は、ねんねの時間でだっこをせがまれても、その必要はないと思います。まず、子どもにとっての睡眠のルーティンを決めてあげて、それ以外のことはとにかくしない。 例えば、外に出て親のだっこひもで眠るのが、その子のルーティンになってしまうかもしれません。1回外に連れていくだけで、そのルーティンを教えていることにもなります。
子ども自身が見通しを持てるように声をかけていく
回答:工藤佳代子さん 夜だけでなくて、昼間の遊びや食事も含めてのリズムを作っていくといいのではないかと思います。 また、上のお子さんの様子を見ると、とても頑張っていると感じます。新しい家族が増えることは、大人は見通しを持てますが、子どもにとって言われても理解が難しいのです。毎日が新しい刺激の連続になるので、そういったことに向き合っているのだと思います。 今は夜泣くことをなんとかしようと思うかもしれませんが、上の子も小さいなりにわかるので、見通しを持てるように声をかけることも大事です。「もうすぐ赤ちゃんはおっぱい飲むからね」「朝になったらお散歩行こうね」など、言葉で伝えていると、だんだん成長と共に理解していくようになります。積み重ねていくことで、子ども自身も見通しが持てるようになります。 2人ともちゃんと成長していくので、また様子が変わっていくと思います。
―― 今回、番組でのアンケートでいちばん多かった声が「パパ・ママが眠れていない」ことでした。パパ・ママの睡眠不足をどう考えたらいいでしょう。
親が十分に睡眠をとることも大事
回答:柳沢正史さん 私のパパ・ママへのメッセージとしては、子育ては大変ですが、自分が睡眠不足にならないように、十分に眠ってくださいと伝えたいです。親の所作や顔色にあらわれるなど、親のストレスが子どもに伝わってしまいます。
りんたろー。さん(MC) 仕事が夜遅く終わって、次の日が早いときに、「早く寝てくれ」という気持ちで寝かしつけることがありますね。
丸山桂里奈さん(MC) あるよね。「ほんとに寝てくれ」という気持ちでやっちゃいます。
りんたろー。さん(MC) こういうものは、子どもに伝わってしまうのですか?
できるだけ親自身もリラックスした状態で寝かしつける
回答:工藤佳代子さん ダイレクトに伝わると思います。子どもにはゆるんでほしいと思いながら、向き合っている大人は力が入って、どちらかというと交感神経にスイッチが入ってしまいます。肌で感じている子どもにとっては、なかなかリラックスできる状態ではないですよね。 難しいとは思いますが、子どもと眠りにつくときは、できるだけ親自身もリラックスした状態で、「今日も気持ちよかったね、1日お疲れさま」という気持ちで迎える。子どもにとっても、心地よい時間になると思います。
PR