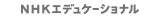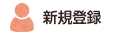一晩に夜泣きが何度もある… どうしたらいい?
4か月のころから夜泣きが多くなりました。多くて5回ぐらいです。泣いたら寝かせたままトントンして落ち着かせて、泣きが激しいときは1回だっこ。泣いて寝なかったら寝つくまでだっこして、ベッドに置いています。以前は、だっこしなくても寝れていたので、だんだん敏感になって寝るのが苦手なのかもしれません。昼と夕方もだっこしながら寝かせていて、1日に合計12時間ぐらい寝ています。できれば夜泣きがなくなってほしいなと毎日思います。
(お子さん7か月のママ)
(お子さん7か月のママ)
丸山桂里奈さん(MC) 大変ですよね、「もうわかる!」と思いました。
りんたろー。さん(MC) うちは1歳2か月ぐらいですが、夜泣きが復活してきました。今までは、僕がだっこすれば寝てくれましたが、ママじゃないとだめになって。ママの比重が多くなるのが心苦しいです。
すくすくファミリー(お子さん2人のパパ) 1人目のときは同じような状況でした。私が夜仕事から帰ると妻がだっこで寝かしつけをしていることもありました。寝かせて、また起きての繰り返しです。2人目がいると、上の子を起こさないように気をつけて、泣いた子をだっこして部屋を移動したり、だっこひもで散歩したりしていましたね。
自分で眠ることを再学習することも大事
回答:柳沢正史さん パパもママも、夜泣きは大変だと思います。子どもが泣くと、反射的にだっこしたり、場合によっては授乳したりしますよね。6~7か月以降になると、子どもの泣きにも種類があることがわかってきます。おなかがすいているのか、不快なことがあるのかなどです。そういった泣きではなく、何かのきっかけで起きてしまうときもあります。 そういったときに、いつもだっこすることで、親のだっこで寝つくことが癖になっているとも考えられます。そのため、自分のベッドで、自分で眠ることを再学習するという考え方もあります。 例えば、寝ついてからベッドに入れるのではなく、赤ちゃんが眠そうになったら、まだ寝ついていない状態で、その子にとって心地のよいベッドに入れて、「自分のベッドは心地がよくて眠る場所」と覚えてもらうわけです。
生活リズム、ルーティンを大事に
回答:柳沢正史さん 生活リズムを整えて、赤ちゃんなりのルーティンを整えることも大事です。例えば、最初はトントンして、体に触ってあげて、落ち着くまでいる。次の日は、トントンを3分間ぐらいで、だっこはしない。その次の日はもう少し延ばしていく。1~2週間かけて、だんだん時間を延ばしていくと、多くの赤ちゃんが自分で眠れるようになります。
夜の睡眠は昼間の過ごし方が影響する
回答:工藤佳代子さん 夜眠れないのは、パパもママもつらいことですよね。一方で、大きくなっていく過程の中では、どうしてもある時期です。 4か月ごろから眠れなくなってきたのは、昼間の過ごし方が影響しているかもしれません。今まで気づかないようなところに気がつき、刺激を受け、夜、目が覚めているのではないかと思います。 例えば、保育園でサンタさんや節分の鬼など、イベントがあった日は、夜泣きをする子が多いのです。それが楽しいことであってもです。そのため、親が「なんで今日はこんなに泣くの?」と思わないように、「今日はサンタさんに会って、ドキドキしたけど楽しかったから、夜泣きがあるかもしれません」と伝えています。 夜だけが独立しているのではなく、昼間の生活もつながって夜の睡眠があると考えて、子どもの気持ちに寄り添ってみてください。
だっこから布団に寝かせるときのポイント
解説:工藤佳代子さん

だっこから寝かせるとき、赤ちゃんの頭から先に布団におろすと、頭が下になり不安を感じてしまいます。
まず、お尻を布団につけて、背中、頭の順に寝かせると起きずに寝られます。試してみてください。

―― 赤ちゃんは、どれくらい眠ればいいんでしょうか?
お昼寝の時間も含めた睡眠時間の目安がある
回答:柳沢正史さん もちろん、幼い子どもは、たくさん眠らないといけません。いろんなガイドラインで推奨される、お昼寝も含めたトータルの睡眠時間があります。0~3か月だと14~17時間、4~11か月ぐらいだと12~15時間です。月齢・年齢とともに減っていきます。睡眠時間は、個人差が大きいものですが、十分なトータルの睡眠時間をとることは大事です。
その子にとって気持ちよく過ごせるリズムが大切
回答:工藤佳代子さん 眠るタイミングや眠り方にも個人差があります。この月齢だったら、この時間帯に何時間寝るというマニュアルがあるわけではありません。 保育園では、昼間の睡眠はあくまで夜の睡眠を補うものというのが基本的な考え方です。昼、寝てしまうことによって、夜の睡眠に影響するのは本末転倒なのです。 園で見えているのは保育園での生活、家庭で見えているのは家での生活なので、園と保護者のコミュニケーションが大事になります。特に小さい子どもは自分で話すことができません。家で何を食べて、お風呂は何時に入って、何時ごろ寝て、夜泣きは何回か、朝は何時ごろ起きたかなど、細かく連携をとりながら、その子にとって気持ちよく過ごせるリズムを探っていきます。
PR