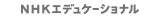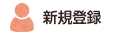子育てルールの違いに悪影響はある?
朝、ママは息子(4歳)に保育園の準備をするよう声かけをします。準備するものを自分で確認できるチェックボードも手作りしました。自分のことは自分でできるように、今はできなくても「こういうことをする」とわかってもらえれば自然にできるようになると考えています。
一方でパパは、息子の荷物を準備したり、着替えを手伝ったり。効率を重視し、叱るなどはもう少し成長してからで、今は家庭がたのしいと思ってもらうことを第一に考えています。
どちらも子どものことを思ってのことですが、このルールの違いで、子どもの成長に悪影響はないのでしょうか。
(お子さん4歳・2か月のママ・パパ)
一方でパパは、息子の荷物を準備したり、着替えを手伝ったり。効率を重視し、叱るなどはもう少し成長してからで、今は家庭がたのしいと思ってもらうことを第一に考えています。
どちらも子どものことを思ってのことですが、このルールの違いで、子どもの成長に悪影響はないのでしょうか。
(お子さん4歳・2か月のママ・パパ)
ルールの違いよりも、夫婦関係の悪さが影響する
回答:帆足暁子さん ルールの違いそのものより、お互いが「自分のほうが正しい」と主張して夫婦関係が悪くなることが、子どもにとってよくありません。今の子どもたちは不安がとても強く、自分のことで両親がぶつかっていると、「ぼくが悪い子で嫌われている」「ぼくがダメなんだ」と受け止めてしまうかもしれません。
夫婦が尊重し合って意見すれば子どもは安心する。生きる力の基盤ができる
回答:帆足暁子さん お互いに、子どものためにどう考えているかを話しながら、「こうしていこう」「ここはゆずれないからこうするよ」など、意見を調整する姿を見せていけば、子どもは「ぼくがダメだから、パパとママがケンカしている」と思わなくてすみます。 家庭でママとパパがたのしそうにして、お互いを尊重し合って意見していけば、子どもは安心できて、生きる力の基盤ができます。意見が違っても、すり合わせていくやり方を見せていくことが、子どもがソーシャルスキルを学習するひとつの機会になるかもしれません。
「子どもが大事」が根底にあれば、ルールの違いは子どもにとって選択肢になり得る
回答:小﨑恭弘さん 例えばママは安全を考えて「危ないからやめて」と言って、パパはチャレンジが大事と考えて「もう少し頑張ってみたら」と言ったとしたら、子どもは考えますよね。この場合、どっちにしても褒められるわけです。やめたら「えらいね」と言われ、やってみたら「できたじゃない!」と。 そういう選択ができる中で子どもたちは育っていくと思うと、夫婦で「子どもが大事」という根底があれば、その関わりやルールに幅や選択肢があってもいいのではないでしょうか。とてもすてきなことだと思います。
PR