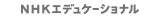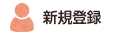親になって1年 りんたろー。と悩みや気づきを語りあう! 後編
番組のMCをつとめるりんたろー。さんのお子さんが1歳になりました。親になって1年目の悩みや気づきを、すくすくファミリーと一緒に、2回にわたってリアルなパパライフを語り合います。

専門家: 井桁容子(元保育士) 川田学(北海道大学大学院 准教授/発達心理学)
親になってパートナーは変わった?
出産して母になったパートナーは変わった?
お子さん7歳・4歳・6か月のパパ 強くなった… 進化した? というか、人間としてバージョンアップしたように感じます。
お子さん6歳・4歳のパパ 子どもが生まれると、一気にたくましくなりますよね。夫婦としてお互いを見ていたのが、妻は子どもが最優先になりました。私はすぐにそうはなれなくて。
お子さん10歳・8歳・4歳・2歳のパパ 女性は強制的に体が変わって、授乳もするし、急に宇宙に放り込まれたような、やらざるを得ない状態になることを、そのときは理解していなくて、ただ「変わった」と思ってしまった。でも、きっと妻は一生懸命変わろうとしていたのでしょうね。私はそれに追いつけず、今思うとギャップがあったんですよね。
りんたろー。さん 「こんな頼りになるんだ!」という気持ちになりました。でも、どうしてもピリピリしている部分はあります。以前は、ママを名前でスマホに登録していたのが、今は「ボス」に変わってます。
ママはどうみてる? 子育て中のパートナーとの関係
妻は母になってたくましくなったと感じているパパ。そんなパパたちは、ママからはどうみられているのでしょうか。
すくすくファミリー(お子さん3人)のある日曜日の様子を見せてもらいました。
パパは仕事が不規則でふだんはあまり家にいませんが、今日は日曜日。やることが多い朝はママと分担し、パパは次女に離乳食。午前中は家族の用事でお出かけ。合間には、遊び場でダイナミックに遊びます。
帰宅後は、昼食の準備です。パパのつくったチャーハンに、子どもたちもおいしそう。
昼食のあと、パパは長女の髪を結んで、上の2人を連れて公園へ。 パパが体をはって子どもと遊んでいる間、ママは家で片付けや次女のお世話をします。 今のパパは、ママからみてどうなんでしょう。話を聞いてみました。 <ママ> 「一緒に育児をする」ことがいちばん大切だと思っていて。パパは3人目になっていろいろわかるようになってきたのか、進んで一緒にしてくれることが増えました。私が疲れていると、察して洗濯物をたたんでくれるなど、「一緒に育児をしている」と実感できることがうれしいです。最初は、やっぱり「手伝う」という感覚があったんです。 1人目が生まれたころ、パパは今以上に忙しく、夫婦で気持ちがすれ違うことが多く、ママもつらい時期があったそうです。そんなパパの転機になったのは、初めて子どもを任されて1時間外出したことでした。 <ママ> 1時間でも子どもをひとりで見ることで責任感を持てたと思います。「ママはこうして1日を過ごしているんだ」とわかったことで、子どもともコミュニケーションがとれるようになり、私も穏やかな気持ちで子どもたちと向き合えます。 <パパ> ひとりで全責任を負わなきゃいけないと不安が大きかったです。それまではママに頼ってしまっていたので、今思うと、これを乗り越えたことで、自分の子どもを見ること、一緒に過ごすことへの不安がなくなったと感じます。 子どもが生まれる前と今。パパとの関係は変わったのでしょうか。 <ママ> 信頼感が高まりましたね。はじめは言えなかったことも言えるようになったり、何かあったら「これはやってくれる」と思えます。1人目、2人目も頼ってきたけど、3人目で心から頼れるようになりました。 時間がない中でも、一緒に子育てするためには、まずパートナーとのコミュニケーションが大事なんですね。
りんたろー。さん コミュニケーションは大事ですよね。
丸山桂里奈さん 疲れているときなどに察してもらえると、とても助かりますよね。
川田学さん 仕事で時間が少ない中、パパは最大限のことをしていると思いますよ。尊敬します。できることを少し努力してやってみて、困ったことやわからないことがあればコミュニケーションして、「交通整理」の時間をつくる。難しいことですが必要だと思います。 整理しないと、だんだんわけがわからなくなって、すれ違いが起こりやすくなります。夫婦で「交通整理」する時間をつくれるように、ときにはサポートを家族の外に頼むのも大事ですね。
井桁容子さん 大事なことは、パートナーが安心することです。「どうすれば安心できるのか?」と考えてみるといいですね。ママが安心するとパパも安心して、安心している大人の雰囲気が赤ちゃんを落ち着かせます。関わる時間の長さよりも、どうすればお互いに安心できるか想像することが大事だと思います。
コミュニケーションで気をつけたいこと
井桁容子さん ママたちが「わかってほしい」「察してほしい」と言いますが、パパも疲れているときにはハードルが高いでしょうね。まず「対話」する、相手をわかろうという気持ちで言葉をかけてみる。言わなくてもわかってくれると思っていたら、いつまでも「交通整理」はできないままもつれてしまいます。「私はこういう理由で、こうしてもらえるとホッとする」のように、具体的に伝えれば、パパもわかって、お互いの思いやりがすれ違いにならなくてすむと思います。
丸山桂里奈さん たしかに、自分が疲れたときに「察してほしい」「気づいてほしい」と言われても難しいかもしれません。自分が思ったことをきちんと伝えるのがいちばんですね。
ママからのお便り
ここで、4人のお子さんのママから届いた、子育ての関わり方についてのお便りを紹介します。
お子さん10歳・8歳・4歳・2歳のママより うちは6人家族で、2~10歳の4人きょうだいです。子育てが始まったころはパパに不満をぶつけてしまい、お互いに理解し合うのが難しいと思う時期がありました。 そこで、細かい家事・育児の内容とタイムスケジュールを「見える化」してパパに伝えました。さらに、家事・育児の中で私が特に負担に感じることを伝えて、お互いに「相手が苦手なこと・嫌なこと」を補い合う形にしました。パパが全ての家事・育児をする日を作って体験したことも、全体像の想像につながったようです。 私がつらいと感じていることを理解して、実行に移しているところ。子どもをかわいがって思いっきりのびのび遊んでいるところ。トイレトレーニングもまるっとやりきっているところ。「さすがパートナー!」と思います。一緒に子育てできていることを実感する日々に感謝しています。
丸山桂里奈さん お便りを読んでいたら自分が言われているみたいで、ちょっとうるっときてしまいました。
りんたろー。さん こんなふうに言ってもらえると、うれしいですよね。ママの言葉はいかがですか?
パパ パパたちは家事・育児の中で「どうしてこれをするのか」理由がわからないときがあると思います。私もそう思うタイプなんですが、ママはそれを理解してくれて、今では理由を言ってくれるようになりました。 我が家の場合、こうなるまでに10年かかっています。何度も衝突して、すり合わせをして、くじけそうになって、やっとうまく回るようになったんです。みなさんも、数回、何か月かうまくいかなかったとしても「もうダメだ」とならなくていいと思います。
丸山桂里奈さん すぐに「もういやだ」「もう無理だ」と思っていましたが、今のパパの話を聞いて、コミュニケーションが大事だなと思いました。
りんたろー。さん 元々は他人だから、家族でもわからないことはたくさんありますよね。
やっぱりコミュニケーションが大事
井桁容子さん コミュニケーションとは、自分の思いを相手にわかるように伝えて、相手の話もきちんと聞くことです。パパもママも、子どもが生まれて、わからないまま親業を背負って、よくわからないところで頑張って、ずれてしまうこともあります。わからなくなったら、自分が納得するより、「この子にとって、どうだろう?」と考えてみる。子育ては、ひとりだけで頑張るのではない、他の人に助けてもらうことは子どもにとってもいいことだという考え方が大事です。
りんたろー。さん 理由を説明してもらえると、「だから必要なんだ」「おろそかにしちゃいけないよね」となるかもしれません。してほしいことを面倒がらずに言ってもらえるとうれしいですね。
丸山桂里奈さん 余裕があれば言える気もするけど…。ママのほうも自分の時間やゆとりを持てれば、パパにも言えたり教えたりできるかなと思います。
りんたろー。さん ただ、寝かしつけやだっこは感覚的で、教えてもらうよりやりながらコツを見つけていくところもありますね。
丸山桂里奈さん たしかに、この子はこの角度がいいとかありますね。
川田学さん 得意なことや苦手なことは人それぞれです。パートナー同士で、常識や形にこだわらずに話し合って、今の生活の中で、どこを誰がやっていくと乗り越えられそうか、お互いの得意なことや苦手なことを確認して、補い合う形でできるといいですね。子どもへの関わり方も夫婦で違うこともありますが、子どもにとっては多角的な経験になり、対応力も育つかもしれません。 今の子育ては、パパママが子どもだったころと比べて「父親はこうすればいい」「母親はこうすればいい」といった正解のモデルがありません。たとえばだっこも、マニュアル通りより、子どもとの関係、家族との関係で合う方法をみつけていく。いま、子育て真っ最中のすくすくファミリーのみなさんは、正解のモデルがない中で、それぞれの家庭で試行錯誤しながらチャレンジしていますね。大変ではあるけれど、そういう意味での楽しさもある時代だと感じています。
今回のパパたちの語り合い、どう思った?
りんたろー。さん 励まされたし、とても共感しました。パパとしてはまだ1年生なので、いい機会だったと思います。
お子さん10歳・8歳・4歳・2歳のパパ 共感できるところが多いですね。専門家の方の話にもあったように、社会も変わってきています。上の世代の人たちには「子育てを手伝わないといけないよね」「イクメンだね」などと言われることがありますが、「"手伝う"じゃないだろう」と少し腹が立つこともあります。私たちの世代はそうなってきていると思うので、プライドを持って子育てしていきたいと思います。
お子さん1歳5か月のパパ 今まさに、自分自身が「パパの正解ってなんだろう」と思いながら育児しているところで、今後の参考になる話がたくさんでした。私が思っていることは、みなさんも同じように思っているんですね。
お子さん1歳5か月のママ パパの本音は、夫婦では聞くのを遠慮してしまうけど、パパ同士で話していると「やっぱりそう思っているよね!」とわかってよかったなと思います。
お子さん6歳・4歳のパパ 子育てはどううまく人に頼っていくかと改めて考えさせられました。ぜひこのメンバーで2次会にいきたいですね。
お子さん7歳・4歳・6か月のパパ うちもまわりに頼ってどうにか成り立っているので、頼ることは恥ずかしいことじゃないと知れてよかったです。とにかく子育ては楽しいです!
パパだけのリモート2次会
スタジオ収録後のある夜、パパだけで「リモート2次会」が開催されました!
趣味とのつきあい、どう変わった?
りんたろー。さん 子どもが生まれる前は、よく服を買いに行ったり、サッカー、バイクでツーリングにも行って自分の趣味を楽しんでいました。でも子どもが生まれたら自分の中でしっくりしない部分が増えて、しなくなってきました。今は、赤ちゃんのスニーカーを買いに行ったり、赤ちゃんを連れてスタジアムに行ったり、自然と赤ちゃん込みの趣味になっています。そういうものでしょうか。
お子さん1歳5か月のパパ はじめは、やっぱり違和感がありましたね。「我慢しなきゃいけない」と思っていたのですが、家族の関わりで今までとは違う楽しさを見い出してきました。元々野球観戦が趣味でしたが、今は子どもを連れて行くようになり、妻も巻き込んで、家族みんなの趣味になっていますね。
お子さん7歳・4歳・6か月のパパ 子どもが中心に変わってくるので、自分だけが楽しいものというより、妻や家族を含めて楽しめるものに変わっていくと思います。
お子さん10歳・8歳・4歳・2歳のパパ みなさん、えらいですね。私はどちらかというと、子どもと一緒にということもなく、我慢している気持ちがありました。
お子さん6歳・4歳のパパ 私はスノボをしていたのですが、子どもが生まれて行かなくなりました。今は、子どもが興味をもったものが、自分の趣味に近くなっています。例えば、昆虫など子どもの好きなことを一緒に楽しむうちにいろいろと視野が広がった気がします。
りんたろー。さん 子どもが成長したら、いつかは一緒にできるのかなと思っています。
お子さん7歳・4歳・6か月のパパ 趣味の復活といえば、野球観戦です。まだ現地には行けていませんが、私が熱を入れてテレビで応援しているので、 長男が応援歌を覚え始めました。親子でキャッチボールもできるようになりましたね。続けたいかどうかは子ども次第ですが、自分が親としていたことを子どもとできるのはうれしいです。
お子さん6歳・4歳のパパ 想像するとワクワクしてきますね。これから楽しめる気がします。
これから先のこと
りんたろー。さん 今、子どもが1歳ぐらいですが、1歳のうちに「やっておいたらいい」ことはありますか?
お子さん7歳・4歳・6か月のパパ おむつ替えやお風呂など、できる限りスキンシップをしたほうがいいと思います。妻に、そこから信頼関係が生まれて、その後に生かされると言われました。いま子どもたちが「パパ大好き」と言ってくれるのは、そのおかげだと自分では思っています。
お子さん10歳・8歳・4歳・2歳のパパ まずは早寝早起きですね。あとは絵本です。本をたくさん読むと、語彙が増えているように思います。小学校に入っても本好きに育っています。
お子さん6歳・4歳のパパ こうしてシェアできるのは、すごくいいことだなと思いました。
お子さん10歳・8歳・4歳・2歳のパパ こういう会は貴重ですよね。いちばん子どもが多くて先輩みたいな雰囲気でやらせてもらえて気持ちよかったです。
お子さん7歳・4歳・6か月のパパ 大先輩ですよ。
りんたろー。さん 今回は、貴重な機会をもらいました。子どもの年齢が違うので、いろいろな話が聞けていいですね。子どもが生まれる前は「自分の役目は(子育てよりも)仕事をがんばること」みたいな感じになってしまうタイプの人間でした。もしこの番組に関わっていなかったら、そんな自分に違和感がないままで、今ほど子育てにかかわっていなかったかもしれません。 こうしてみなさんと接して、いろんな選択肢があることを教えてもらえている。その選択肢の中から合うものを選びながら、自分も父親として成長していけたらいいなと思っています。
PR